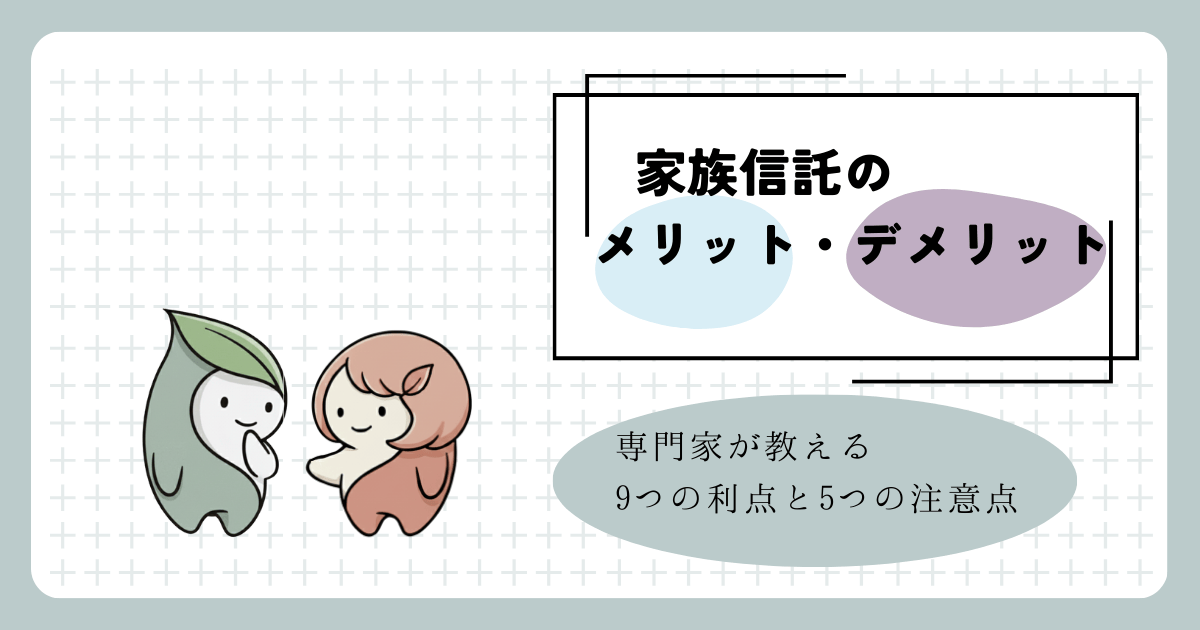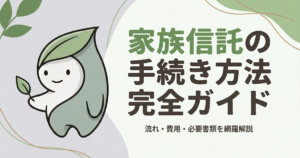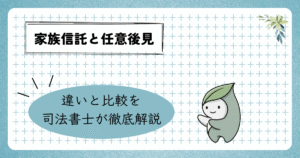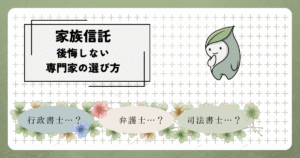週末、久しぶりに訪れた実家のリビング。父が「最近、どうも物忘れが多くてな」と笑う隣で、母が一瞬だけ不安そうな顔をした。
帰り道、私の頭の中は、さっきの母の表情でいっぱいだった。「もし、父の認知症が進んでしまったら…。将来、施設に入るときに実家を管理したり売却が必要になってもできないと聞いたことがある。母の生活費も、父の口座が凍結されておろせなくなってしまうんじゃ…」
そんな時、ふと頭に浮かんだのが「家族信託」という言葉。それは、今の私の不安にとって、一つの答えになるかもしれない選択肢でした。
しかし、その一歩がなかなか踏み出せない。ネットで調べても難しい言葉が並ぶばかりで、肝心のメリットとデメリットが明確に分からないのです。家族の大切な財産に関わることだからこそ、良い点も悪い点も全て知った上で判断したい。そんな思いだけが募っていきました。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するため、家族信託のメリットとデメリットを専門家がどこよりも分かりやすく解説していきます。
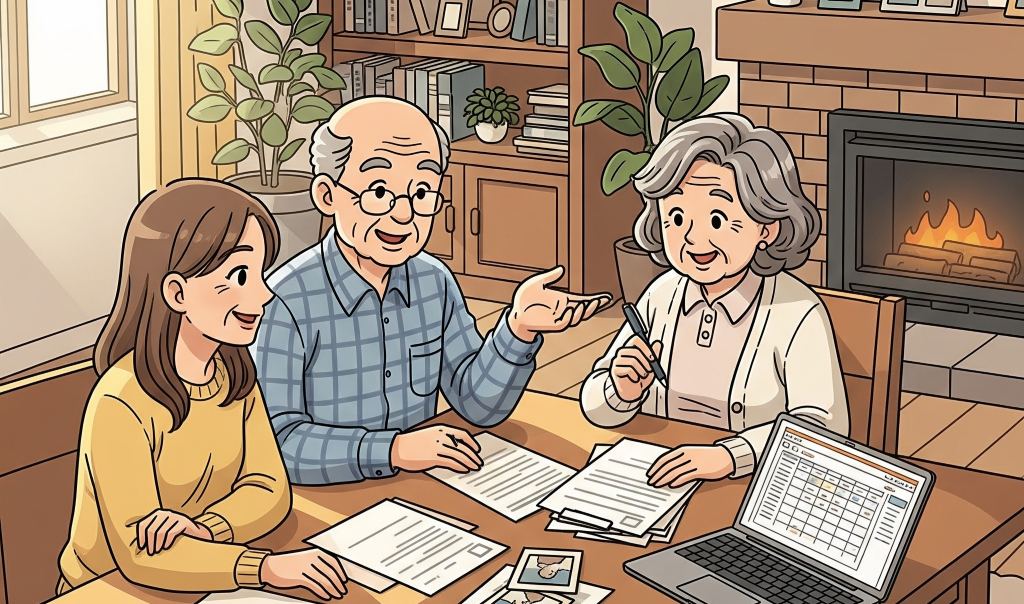
家族信託とは?3人の登場人物で理解する基本の仕組み
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理・処分を託すための法的な契約です。元気なうちに財産の管理方法を決めておくことで、将来の認知症などによる判断能力の低下に備えます。
この仕組みは、3人の登場人物で成り立っています。
- 委託者(いたくしゃ):財産を託す人(例:親)
- 受託者(じゅたくしゃ):財産を管理・処分する人(例:子)
- 受益者(じゅえきしゃ):財産から生まれる利益を受け取る人(例:親)
※委託者と受益者は同一人とすることが可能
財産の名義は子に移りますが、委託者と受益者が同じであれば、家賃収入やご自宅に住む権利などの利益は引き続き親が受け取るため、贈与税を心配することなく、生前からスムーズな財産管理の準備が始められます。
家族信託の9つの主要メリット
家族信託が持つ、他の制度にはない強力なメリットを9つご紹介します。
-
【最大のメリット】認知症による「資産凍結」を回避できる
判断能力が低下すると、銀行口座からの出金や不動産の売却が一切できなくなる「資産凍結」状態に陥ります。家族信託があれば、受託者である子が契約に基づき財産を動かせるため、介護費用や生活費の支払いが滞る心配がありません。
-
成年後見制度より柔軟で迅速な財産管理が可能
家庭裁判所の監督下にある成年後見制度と違い、家族信託は家族間の契約です。裁判所や成年後見人などの第三者の介入を受けることなく、収益不動産の売却や建て替えといった積極的な資産活用も、契約の範囲内で迅速に行えます。
-
信託終了時の財産の承継先を指定できる(遺言の代用)
信託契約が終了(例:最後の受益者の死亡)した際に、残った財産を誰に渡すかをあらかじめ指定できます。この指定された人を「帰属権利者」と呼びます。これにより、信託していた財産については遺産分割協議の対象から外れ、円滑に最終的な承継者へ財産を引き継がせる、遺言のような機能を持たせることができます。
-
「二次相続」以降の承継先を指定できる
遺言では一代先までしか財産の行き先を決められませんが、家族信託では「私が亡き後は妻へ、妻の亡き後は長男へ」というように、数世代にわたる資産承継の道筋をつけることも可能です。
-
不動産の共有持分も「資産凍結」から守れる
不動産が夫婦の共有名義になっている場合、どちらか一方でも認知症などで判断能力が低下すると、不動産全体の売却や活用ができなくなります。夫婦それぞれが自分の持分を、信頼できる一人の受託者(例えば子など)に信託しておくことで、受託者が単独で不動産全体の管理・処分を行えるようになります。
-
家族の状況に合わせた自由な設計が可能
家族信託は契約であるため、「長男には事業用の土地を任せたい」「次男には現金を任せたい」といったように、家族の実情に合わせて財産の管理や承継のルールをオーダーメイドで柔軟に設計することができます。
-
倒産隔離機能で信託財産が守られる
万が一、財産を管理する受託者(子)が自己破産しても、信託された財産は差し押さえの対象になりません。あくまで委託者(親)の財産として独立して守られます。
-
スムーズな事業承継を実現できる
会社のオーナー経営者が認知症になると、保有する自社株の議決権が凍結され、役員の選任や銀行からの融資といった経営上の重要判断ができなくなります。株式を後継者に信託しておくことで、経営の空白期間を生むことなく、安定した事業承継が可能になります。
-
障がいを持つ子の「親なき後」の生活を守れる
「福祉型信託」とも呼ばれ、親が亡くなった後も、信頼できる受託者が子どものために財産を管理し、生活費を定期的に給付する仕組みを作ることができます。
契約前に知るべき5つのデメリットと注意点

家族信託は非常に強力で魅力的な制度ですが、いくつか知っておくべき留意点があります。大切なご家族と財産を守る最善の選択をするために、ここからは注意すべき点についても一緒に見ていきたいと思います。
-
専門家への費用(初期費用)がかかる
オーダーメイドの契約書作成や登記手続きのため、司法書士などの専門家への報酬が発生します。財産額や内容によりますが、一般的に50万円~100万円程度の初期費用が見込まれます。
-
受託者の負担と責任が非常に重い(無限責任)
財産を預かる受託者には、帳簿の作成や報告といった事務的な負担に加え、法律上の重い責任(善管注意義務)が伴います。
さらに、信託したアパートの壁が剥がれて通行人にケガをさせてしまうなど、信託財産の管理が原因で第三者に損害を与えた場合、その賠償責任は信託財産だけでは終わりません。損害額が信託財産の額を上回れば、受託者は自己の個人資産をもって賠償しなければならず、これを「無限責任」と呼びます。
この重い責任を引き受けてくれる家族への十分な説明と理解が不可欠です。
-
あくまで「財産管理」の制度(身上監護は対象外)
家族信託は、あくまで財産の管理や承継を目的とした制度です。そのため、親の介護施設への入所契約や入院・手術の同意といった、本人の代理人として行う法律行為(身上監護)は、受託者の権限には含まれません。
この「身上監護」も将来に備えて任せたい場合は、家族信託とよく比較される「任意後見制度」を併用するという選択肢があります。どちらの制度がご自身の状況に適しているか、ぜひこちらの記事でご確認ください。
-
損益通算ができない
信託した収益不動産(アパートなど)で赤字が出た場合、信託に含まれないほかの不動産の所得などと合算して税負担を軽くする「損益通算」ができません。これは税務上の重要な注意点です。
-
税金の特例「空き家控除」が使えなくなる
親が亡くなった後に、実家を売却する際の税金が大幅に軽くなる「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」(通称:空き家控除)が使えなくなる可能性があります。
この特例は「昭和56年5月31日以前に建てられた建物」で「相続で家を取得したこと」などが適用条件ですが、信託された家は「信託契約」に基づいて引き継がれるため、この条件を満たせず控除の対象外となるのです。
将来的に古いご実家を相続して売却する際、これは非常に大きなデメリットになる可能性があります。もしご実家がこの特例の適用条件に当てはまる場合は、信託を組むことで将来大きな税負担を負うリスクがあるため、特に慎重な検討が必要です。
【比較表】家族信託・成年後見・遺言の違い
| 機能 | 家族信託 | 成年後見制度 | 遺言 |
|---|---|---|---|
| 生前の財産管理 | ◎ 柔軟に可能 | △ 裁判所の監督下で可能 | × 不可 |
| 資産凍結対策 | ◎ | ○ | × |
| 死後の財産承継 | ◎ | × | ◎ |
| 身上監護 | × | ◎ | × |
結論:家族信託は、元気なうちの「転ばぬ先の杖」
家族信託は、認知症などによる資産凍結への最も有効な対策の一つであり、柔軟な財産管理を実現できる画期的な制度です。しかし、専門家のサポートが不可欠であり、費用もかかります。
「うちはまだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ、準備を始めるベストなタイミングです。手遅れになって後悔する前に、まずは一度、専門家に相談することが第一歩です。では、その専門家とは一体誰に相談すれば良いのでしょうか。こちらの記事で、あなたに最適な専門家選びのポイントを詳しく解説していますので、ぜひ続けてお読みください。