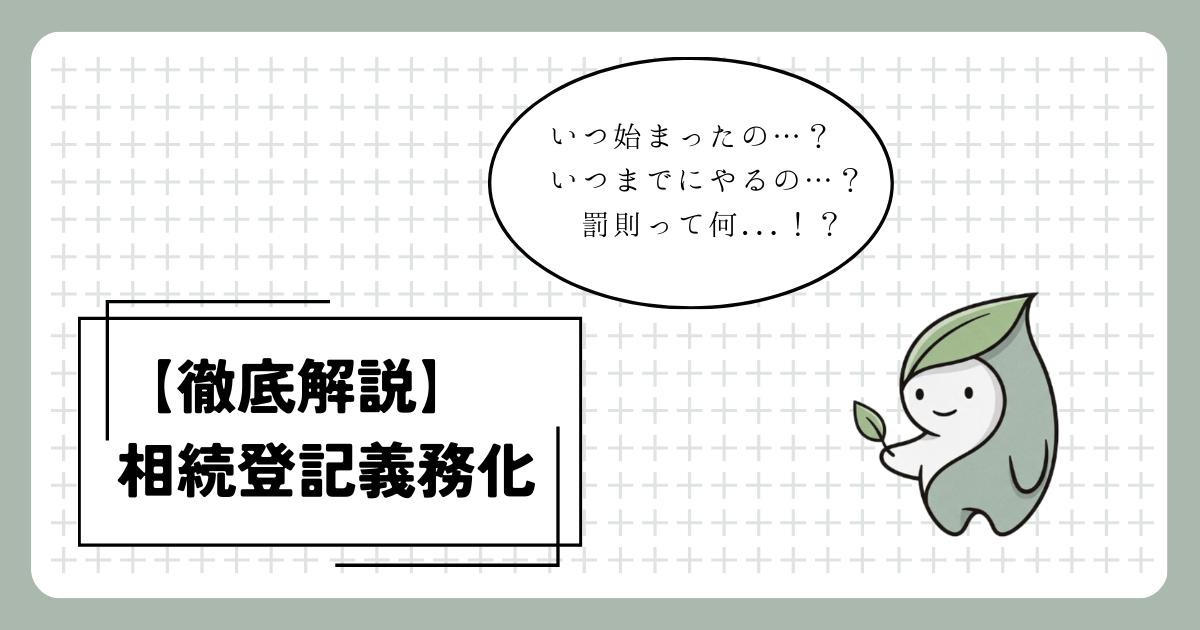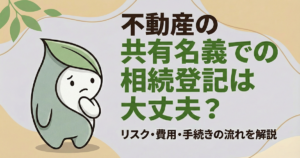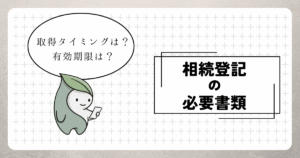相続登記は2024年4月1日から義務化されました。罰則として、原則3年以内の期限に遅れると最大10万円の過料の対象になり得ます。
「実家の名義が祖父のまま…」そんな不安に対し、相続登記の専門家である司法書士が、いつまでに・何をすべきか・放置のリスクをわかりやすく解説します。
「そういえば、実家の名義は亡くなった祖父のままかもしれない…」
もしかしたら、あなたも記憶の片隅でそう感じたことがあるかもしれません。先祖代々の土地や、親が暮らした大切な家。その名義変更は、これまで「いつかやればいいこと」でした。
しかし、その“いつか”には、法律上の明確な期限が設けられました。2024年4月1日、相続登記が義務化されたのです。
この法改正は、決して他人事ではありません。「いつまでに?」「何をすれば?」「罰則はあるの?」こうした切実な疑問に、相続登記の専門家である司法書士が、あなたに寄り添いながら分かりやすく解説します。
相続登記の義務化はいつから?→2024年4月1日からスタート
相続登記の義務化を定めた改正不動産登記法は、2024年(令和6年)4月1日から施行(スタート)されました。
したがって、この日以降に発生した相続はもちろん、過去に発生した相続もすべて義務化の対象となります。「うちは何年も前に亡くなった親の相続だから関係ない」ということにはなりませんので、十分にご注意ください。
登記の申請期限はいつまで?→「3年以内」がルール
義務化に伴い、相続登記には申請期限が設けられました。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。
少し難しい表現ですが、要するに「自分が相続人となり、不動産を相続したことを知ってから3年以内」ということです。多くの場合、これは「被相続人(親など)が亡くなったことを知ってから3年以内」と考えてよいでしょう。
この期限は、いつ相続が発生したかによって起算日(カウントの開始日)が異なります。
【救済策】期限に間に合わない場合の「相続人申告登記」
「3年以内に遺産分割の話し合いがまとまらない」というケースでもご安心ください。新たに設けられた「相続人申告登記」という簡単な申出を法務局に行うだけで、ひとまず登記義務を果たしたと見なされ、過料の心配はなくなります。
この手続きは相続人の一人が単独で行うことができます。
これから相続が発生する場合
【期限】
自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内
【具体例】
2025年10月1日に親が亡くなり、その事実を同日に知った場合
→ 2028年9月30日までに相続登記を申請する必要があります。
過去に発生した相続の場合(義務化より前の相続)
【期限】
「2024年4月1日の義務化施行日」と「自分が不動産を相続したことを知った日」のいずれか遅い方から3年以内
【具体例】
2015年に亡くなった祖父名義の不動産を相続していたことを、相続人がずっと前から知っていた場合
→ 義務化施行日である2024年4月1日からカウントが始まり、2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
【補足】相続人がすでに亡くなっている場合(数次相続)
例えば、上の例で、祖父の相続人である父が登記をしないまま亡くなり、その相続人である子(あなた)が不動産を引き継ぐケースを考えてみましょう。
このように相続が複数重なっている状態を「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。この場合、最終的に不動産を取得した相続人(あなた)が、祖父から父へ、父からあなたへという両方の相続登記を申請する義務を負うことになります。
もし、あなたがこの状況を以前から知っていたのであれば、期限の考え方は上記と同様で、2027年3月31日までに登記を申請する必要があります。
ポイント
過去の相続については、2027年3月31日という最初のタイムリミットが迫っています。心当たりのある方は、お早めに専門家へご相談ください。
【罰則】期限を過ぎるとどうなる?10万円以下の過料について解説
「もし期限内に相続登記をしなかったら、どんな罰則があるの?」というご質問を最も多くいただきます。正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、期限を過ぎてすぐに過料が科されるわけではありません。まず法務局から「登記をしてください」という通知(催告)が届き、その通知に応じて手続きをすれば過料は科されません。過料は、この催告も無視してしまった場合の最終手段とお考えください。
ここで重要なのは、一般に「罰則」と総称されるこのペナルティの法的な性質です。
「罰金」と誤解されやすい「過料」とは?
今回のペナルティを「罰金」だと思われている方もいらっしゃいますが、正しくは「過料(かりょう)」という種類のものです。
この二つの大きな違いは、「前科がつくかどうか」という点です。
- 罰金:いわゆる刑事罰の一種で、前科がつきます。
- 過料:行政上のルール違反に対するもので、前科はつきません。
相続登記のケースで科されるのは「過料」ですので、前科がつくことはありません。その点は、どうぞご安心ください。
「正当な理由」があれば過料は科されない
過料は「正当な理由」がない場合に科されます。その「正当な理由」の例としては、以下のようなケースが挙げられています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する
- 遺言の有効性や遺産の範囲が裁判で争われている
- 申請義務を負う相続人自身に、重病などの事情がある
- 相続人がDV被害者等で、避難をしていて手続きが難しい
- 経済的に困窮しており、登記費用が払えない
個別の事情が「正当な理由」にあたるかどうかは、最終的に登記官が判断します。
例えば、上で挙げた理由にもあるように相続人が非常に多いケースでは、全国から戸籍謄本などを集めるだけで数ヶ月を要することも珍しくありません。
そのため、「やっとの思いで書類を集めても、手続きが終わる前に有効期限が切れてしまうのではないか」というご相談をよくいただきます。相続登記に必要な書類と、それぞれの有効期限については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
関連記事:【相続登記の必要書類】有効期限の完全ガイド|司法書士が解説
まとめ:相続登記の罰則(過料)を避けるために
この記事のポイントをまとめます。
- 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
- 申請期限は、原則として相続を知ってから3年以内
- 過去の相続も対象で、最初の期限は2027年3月31日
- 罰則は10万円以下の「過料」で、前科はつかない
相続登記は、ご自身の権利を守るためだけでなく、次世代に負の遺産を残さないためにも非常に重要です。
手続きには戸籍謄本の収集など、思った以上に時間と手間がかかることも少なくありません。「まだ大丈夫」と思わずに、まずは相続登記の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。司法書士に依頼した場合の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。